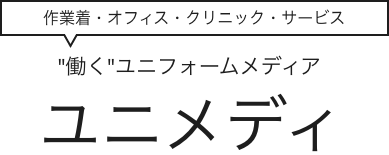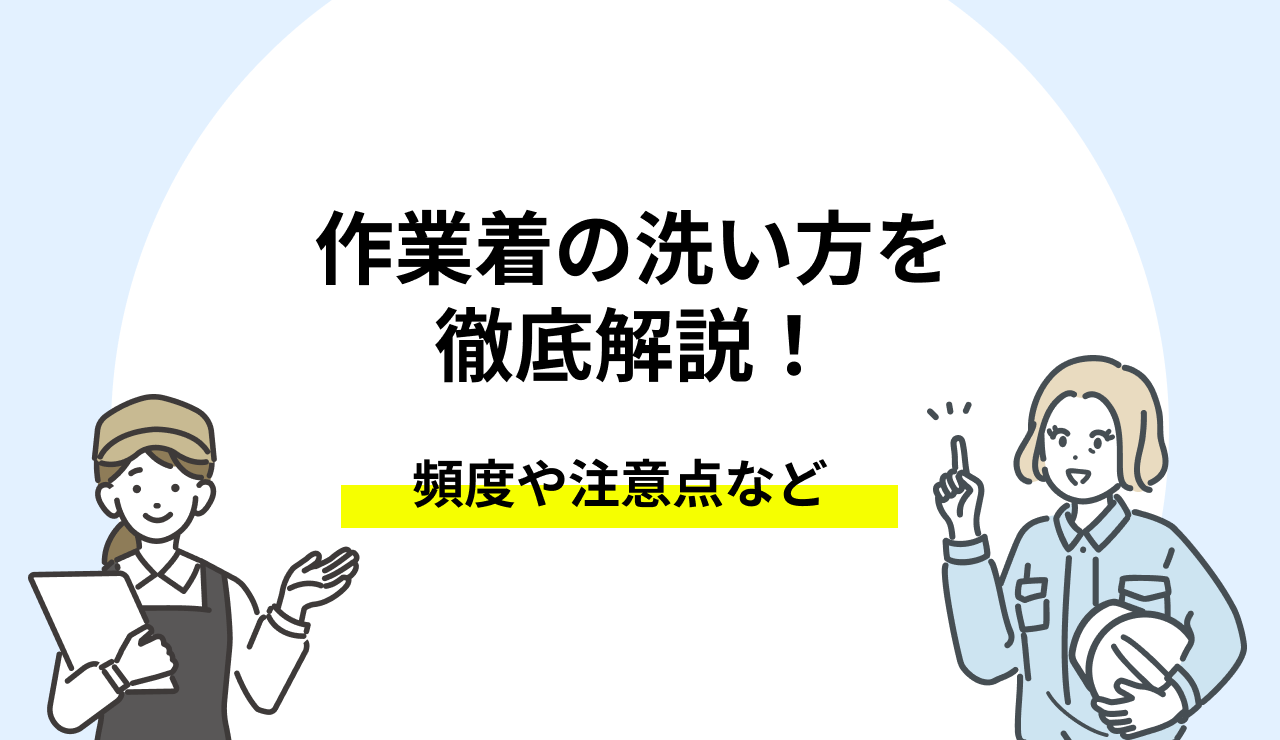作業着は毎日の業務で欠かせない存在ですが、泥や油、ペンキなどの頑固な汚れがつきやすい環境だと、洗濯方法に悩む方も多いのではないでしょうか。間違った洗い方をしてしまうと、汚れが落ちにくくなるだけでなく、生地が傷んでしまうこともあります。
この記事では、汚れの種類に合わせた正しい洗い方や、作業着を長く清潔に保つためのコツを詳しく解説します。大切な作業着を長持ちさせたい方は、ぜひ参考にしてください。
作業着の洗い方【汚れの種類別】
作業内容や環境によって、作業着に付着する汚れはさまざまです。それぞれの汚れに適した洗い方を知ることで、作業着を清潔に保ちやすくなります。ここでは、汚れの種類別に洗い方のポイントを紹介します。
汗・脂汚れ
体を動かさなくても、自然と汗はかいており皮脂も分泌されています。汗や脂は一見目立たない汚れでも、放置すると黄ばみの原因になります。特に襟元・背中・脇などは汚れがつきやすいため、丁寧なケアが必要です。
【洗い方のポイント】
頑固な汚れでなければ、まずは中性洗剤から試します。洗濯用の固形石けんや食器用洗剤などの中性洗剤をつけて、ブラシなどで軽くこすってから洗濯機にかけます。
汚れがひどい場合は、つけ置き洗いするのがおすすめです。ぬるま湯に洗濯用の漂白剤を入れて、1〜2時間つけ置きします。つけ置きした後は、塩素系の漂白剤の場合は水ですすぎ、酸素系の漂白剤の場合は、洗濯洗剤をつけて手洗いします。
黄ばみは、汗や脂が酸化した弱酸性の汚れのため、弱アルカリ性の洗剤(市販の洗濯洗剤やセスキ炭酸ソーダ、過炭酸ナトリウムなど)を使うと効果的です。ただし、洗浄力が強い洗剤は、生地にダメージを与える可能性があるため注意しながら使用してください。
油汚れ
機械を扱う作業で、避けて通れないのが油汚れです。油が作業服につくと繊維に浸透してしまうため、なかなか落ちない頑固な汚れです。
【洗い方のポイント】
油は温めると、やわらかくなる性質があります。そのためお湯で予洗いして汚れを浮き上がらせると効果的です。
まずはバケツなどに、お湯と洗剤を入れて混ぜます。つけ置きに使うぬるま湯の温度は通常40〜50℃が目安ですが、油汚れの場合は60℃くらいの高温でもかまいません。ただしあまりに高温すぎると、作業着の繊維が傷んでしまう恐れがあるため注意してください。
また油は酸性の汚れのため、中和させるアルカリ性の重曹や、油汚れに強い食器用洗剤などを使うのがおすすめです。
作業着を1〜2時間つけ置きしたら、軽くもみ洗いします。流水ですすいでから、通常の洗濯を行います。
汚れが落ちにくい場合やピンポイントで汚れを落としたい場合は、油を溶解させるベンジンやクレンジングオイルを油汚れに直接塗布するとより効果的に落とせます。作業着の下にいらない布を敷いて、上から汚れを歯ブラシなどで叩くと汚れが落ちやすいです。
泥汚れ
屋外作業では、泥や砂が作業着に付着しやすくなります。泥や土、砂は水に溶けない性質があるため、水洗いでは落ちにくいため注意が必要です。作業着の繊維の中に泥などの粒子が入り混んでいるため、これらを洗濯前に取り除かなければなりません。
【洗い方のポイント】
水で洗い流さず、作業着を手ではたいたりブラシで払ったりし、汚れを落とすことが大切です。作業着が濡れている場合は、干したりドライヤーをあてたりして十分に乾燥させると、汚れをかきだしやすくなります。
次にぬるま湯でつけ置き洗いをします。汚れが落ちにくい場合は、固形の洗濯石鹸をすり込むとよいでしょう。つけ置き洗いが終わったら、汚れが繊維に戻らないように水でしっかりとすすいで、洗濯機に入れて洗濯します。
泥汚れに特化した洗濯洗剤もあるため、よく泥汚れが発生する場合は、専用洗剤を用意しておくのがおすすめです。
サビ汚れ
サビ汚れは、鉄くずなどが付着してそのまま酸化したりサビに触れたりすることで、作業着に付着することがあります。サビ汚れがついたまま洗濯機で洗うと、洗濯機内の腐食や劣化にもつながる恐れがあるため、予洗いでサビ汚れをしっかりと落としておく必要があります。
【洗い方のポイント】
サビ汚れは、一般的な洗濯洗剤ではなかなか落ちないため、酸性の洗剤やお酢などを使うのが効果的です。
軽めのサビ汚れの場合は、お酢と食器用洗剤を使います。汚れの部分にお酢をかけてしばらく置き、食器用洗剤でお酢を洗い流し、洗濯機にかければ汚れが落ちます。
お酢と食器用洗剤で落ちない頑固なサビ汚れには、重曹がおすすめです。重曹と水を混ぜてペースト状にし、汚れに塗って2時間ほど置きます。その後にブラシなどでこすれば汚れを落としやすいです。ただし重曹には研磨効果があり、あまりこすると作業着が傷む恐れもあるため注意してください。
ペンキ汚れ
塗装作業などでよく付着するのがペンキ汚れです。ペンキは乾いて固まってしまうとなかなかとれないため、できる限り早く対処することが大切です。
また、ペンキの種類によって適した落とし方も異なるため、まずは水性か油性かを確認してください。
【洗い方のポイント】
水性ペンキの場合、乾く前であれば水洗いと中性洗剤で比較的簡単に落とせます。汚れた部分を水で洗い流し、ブラシで優しくこすります。汚れが残る場合は、スポンジなどに中性洗剤をなじませ、汚れた部分を軽くトントンと叩きながら洗います。
乾いてしまった水性ペンキは、完全に落とすことは難しいですが、汚れを薄くすることは可能です。まず固まったペンキの表面をヘラなどで優しく削ります。次に、歯ブラシでこすりながら少しずつ汚れを落とします。歯ブラシでこするときは、中性洗剤をつけるとより効果がアップします。あとは洗濯機で洗いますが、色移りする恐れがあるため、単独で洗ってください。
油性ペンキの場合は、乾くと汚れが落ちない可能性が高いため、早急に対処するのがポイントです。まずペンキで汚れた部分は、中性洗剤をつけた歯ブラシで叩いて汚れを浮かせます。ある程度汚れを落としてから、水ですすぎます。除光液があれば、汚れにつけてもみ洗いするのも効果的です。
油性ペンキが乾いてしまった場合は、除光液を染みこませたティッシュを押し当てて、歯ブラシでこすります。汚れが浮いてきたら、水ですすいでください。
作業着を洗う際のポイント

作業着はちょっとした工夫で汚れの落ち方が変わり、長持ちさせながら清潔に保てます。作業着を洗う際に押さえておきたいポイントは次のとおりです。
- 泥汚れなどはブラッシングしておく
- つけ置き洗いを行う
- 汚れに合った洗剤で予洗いしておく
- 他の洗濯物とわけて洗う
それぞれ詳しい内容を見ていきましょう。
泥汚れなどはブラッシングしておく
泥や砂、金属片などの粒が大きい汚れがついている場合、あらかじめブラッシングしたりはたいたりして、ある程度汚れを落としておくのがポイントです。汚れが落ちやすくなるだけでなく、洗濯機に異物が入ることを防止できます。
粒の大きい固形の汚れがついたまま洗濯してしまうと、洗濯機の劣化を早めたり故障リスクを高めたりする恐れがあります。洗濯機の寿命を延ばすためにも、異物の混入を防ぐブラッシングを行いましょう。
つけ置き洗いを行う
洗濯機で洗う前に、つけ置き洗いを行うことで汚れが一段と落ちやすくなります。汚れが作業着の繊維内まで入り込んでいると、そのまま洗濯機に入れてもなかなか汚れは落ちません。つけ置き洗いをすることで、繊維の中から汚れが浮きやすくなります。
つけ置き洗いの方法は、40〜50℃のぬるま湯に、1〜2時間ほどを目安につけ置きします。とくに油などの汚れはぬるま湯につけることで、汚れが浮きやすくなります。つけ置き終わって、お湯にまだ汚れがでているようであれば、お湯を交換し、汚れが出なくなるまでくり返します。またぬるま湯に洗剤を混ぜることも、効果的に汚れを落とすポイントです。
汚れに合った洗剤で予洗いしておく
汚れごとの特性は異なるため、どのような汚れかを把握して、それに応じた洗剤を使うことが大切です。
たとえば、油はアルカリ性の重曹や、油汚れに強い食器用洗剤などを使うと効果的ですが、サビ汚れには酸性の洗剤やお酢などが効果的です。また油汚れには温かめのお湯で汚れを浮かせることがポイントである一方で、泥汚れは水分を含ませるとかえって繊維の中まで汚れが入り込んでしまいます。
汚れの特性を理解し最適な方法で予洗いすることで、作業着をよりきれいに保てるでしょう。
他の洗濯物とわけて洗う
作業着は、他の洗濯物をわけて洗うようにしましょう。そのまま一緒に洗うと、他の洗濯物にまで油や泥などの汚れがついたりニオイが移ったりする恐れがあるからです。洗濯機にかける時は、作業着だけで洗うのがポイントです。
作業着を洗う頻度は?
作業着は、毎日洗うのがおすすめです。汚れがついたまま放置すると落ちにくくなってしまい、手間がかかったりクリーニングに出したりする必要が出てきます。その日のうちにすぐに洗濯すれば、手間ひまを最小限に抑えてきれいな状態を保ちやすくなります。
また油やペンキなどの汚れがつきにくい作業だとしても、汗や皮脂などの目に見えない汚れがついて蓄積しています。これらを放置すると黄ばみやニオイの原因にもなるため、予防する意味でもこまめな洗濯を心がけましょう。
作業着は毎日洗うことを前提に、洗い替えとして2〜3着用意しておくとよいでしょう。
作業服を洗うときの注意点
作業着を長持ちさせることはもちろん、洗濯機の故障や肌荒れを防ぐためにも注意しておきたいポイントがあります。
- 洗濯前に洗濯表記を確認する
- ゴム手袋などを使用する
- 洗濯槽は清潔な状態を保つ
- 洗濯した後はすぐに乾かす
それぞれ詳しく解説します。
洗濯前に洗濯表記を確認する
洗濯前に必ず、作業着の洗濯表記を確認してください。作業着によっては使用できる洗剤や水温の上限が決まっていることもあります。確認しないまま洗濯してしまうと、作業着を傷めてしまう可能性があるため注意が必要です。
ゴム手袋などを使用する
作業着をつけ置きや予洗いする際は、ゴム手袋を使用するようにしましょう。素手のまま行うと、作業服についた汚れや洗剤、漂白剤などによって、手が荒れたり乾燥したりする恐れがあります。
洗濯槽は清潔な状態を保つ
作業着を頻繁に洗濯する場合は、洗濯槽のケアを行うようにしましょう。汚れのひどい作業服を頻繁に洗濯していると、洗濯槽の中に特殊な汚れが残って蓄積されてしまいます。このままにしておくと、他の衣類に汚れやニオイが移ったりする可能性もあります。また洗濯槽が汚れたまま洗濯にかけても、洗浄力の効果が最大限に発揮されず、汚れが落ちにくくなることも考えられます。
洗濯槽は、専用のクリーナーを使って定期的なケアが必要です。専用クリーナーによって推奨される目安は異なりますが、2か月〜6か月に1回を目安に洗濯槽をケアしておくと清潔な状態を保ちやすくなります。同じタイミングで、排水口の掃除をしておくと、ニオイ発生やゴミ詰まりなども防止できます。
洗濯した後はすぐに乾かす
作業着を洗濯した後は、すぐに乾かしましょう。濡れたままの状態が長引くと菌が増殖してしまい、カビやニオイが発生する原因となります。
作業着を素早く乾かすには、洗濯機でしっかりと脱水するのが効果的ですが、シワになりやすい懸念もあります。脱水の途中で一度取り出してシワを伸ばすように畳んでから、再度脱水にかけるとシワを軽減できます。
また室内に干す際は、扇風機や除湿機などを使うと効率よく乾かせます。
作業着の洗濯が面倒な人におすすめの方法
作業着を毎日着る方にとっては、予洗いやつけ置き洗いするのが面倒に感じるかもしれません。そのような場合は次の2つの方法を取り入れてみるのがおすすめです。
- 防汚効果のある作業着を選ぶ
- 専門業者に依頼する
それぞれ詳しく見てみましょう。
防汚効果のある作業着を選ぶ
作業着の中には、防汚加工が施されているものがあります。防汚加工された作業着は「汚れがつきにくい」・「汚れが落ちやすい」といった2つを兼ね備えています。
着用中は、生地の表面にある撥水・撥油機能が働くことで、汚れが付着しにくくなります。また、洗濯の際に水に濡れることでその働きが切り替わり、洗濯水が生地に入り込んで汚れが落ちやすくなります。
作業着を清潔に、長く使いたい方は、防汚効果のあるタイプの作業着がおすすめです。以下のサイトでは、防汚効果のある作業着やユニフォームを紹介しているため、ぜひご覧ください。
-

-
防汚効果のある作業着・ユニフォームを探す
通販サイト、ユニフォームの通販ならUniform Worldへ。ワークユニフォーム(作業着、作業服)オフィスユニフォーム(事務服、会社制服、オフィスウェア)、クリニックユニフォーム(白衣、ナース服、医 ...
uniformworld.net
専門業者に依頼するのもおすすめ
作業着を確実にきれいにしたい場合は、専門業者に依頼するのが有効な手段といえるでしょう。金銭的な負担がかかる方法ではありますが、洗濯のプロに任せることで、生地に合った適切な方法でしっかりと洗ってもらえます。
とくに従業員に作業着を貸与している企業であれば、適切な洗い方ができているかどうかは、しっかりと確認しておきたいポイントです。長く着るためにも、クリーニングの手配は検討すべき課題といえるでしょう。
また企業の場合だとクリーニングだけでなく、入退社や転勤などによる作業着の支給・交換といった管理も行わなければなりません。このようにクリーニングや支給・交換などの管理業務は、案外わずらわしく手間がかかるといった悩みを抱える方も少なくありません。
このような場合は、クリーニングから在庫管理に至るまで、作業着の管理を依頼できるサービスの利用がおすすめです。以下のサイトでは、作業着のレンタル・クリーニングサービスを紹介しているため、管理業務担当の方はぜひご覧ください。
-
-
ユニフォーム レンタル・クリーニング関する情報はこちら
『ユニフォーム管理のわずらわしさから解放!!』 入退社が多くてユニフォームの管理に手間がかかる!どのタイミン […]
www.napper.co.jp
まとめ
作業着をきれいに保つには、汚れの種類を見極めて、適切な洗い方を実践することが大切です。泥汚れは乾かしてからブラッシング、油汚れは高めの温度とアルカリ性洗剤、ペンキは早めに対処するなど、それぞれに合った洗い方が必要です。毎日のこまめな洗濯や、つけ置き洗いなどのひと手間をかけることで、清潔で快適な作業着を維持しやすくなります。
また防汚効果のある作業着を選ぶことや、専門業者に洗濯を依頼することもおすすめの方法です。作業着を清潔に、長く着用できるようにしましょう。